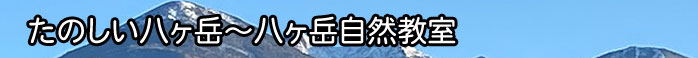|
 |
 |
 |
| 投稿日:2023年4月28日 |
| タイトル:八ヶ岳に住む生き物・ぬり絵図鑑 |
 |
**オオゾウムシ**
ゾウムシの仲間では最大ですが、体の大きさは1cm~3cmと個体差があります。
特徴は象の鼻のように長い口先で名前の由来になりました。体はとても硬く灰褐色のまだら模様で、デコボコして いて足には 鋭い爪があり、しがみつく力が強いです。
日本全国の森や林、里山の木が豊かな場所に住んでいて、マツやスギ等の針葉樹やナラやクヌギなどの樹液をなめて暮らしています。
卵は弱った木や倒木などの湿り気のある物を選んで、その長い口で穴をあけて産卵します。
羽化してからの寿命は2年程です。
|

プリントアウト用PDFファイル(A4縦1ページ:341KB)

|
 |
 |
 |
 |
 |
| 投稿日:2023年4月19日 |
| タイトル:八ヶ岳に住む生き物・ぬり絵図鑑 |
 |
**アズマヒキガエル**
体長6~18センチ。山陰地方北部から島根県東部、近畿地方、東北までに生息。自然の中では寿命の長いもので15年、人が飼育したものでは36年の記録があります。体の大きいものほど行動範囲が狭く、1か所でのんびり暮らしてい ます。ほとんど土の中で寝て過ごし、夜になると3時間ほど食事をしに出てきて主に昆虫などを食べます。
卵は一度に2千個から2万個も産みます。他のカエルと違って小さいうちに変態(オタマジャクシからカエルになるための体の変化)してカエルになる。変態したての大きさは1cmくらい!とても小さい!
そして、生き残れるのはなんと!1万匹に一匹?多くは魚や鳥やヘビ、水生昆虫などに食べられてしまうけれど、他の沢山の生き物達 の命を支える役割も果たしています。
冬は冬眠して、また春になると水場へ来て沢山の卵を産みます。これがアズマヒキガエルの一年の暮らし方です。
|

プリントアウト用PDFファイル(A4縦1ページ:445KB)

|
 |
 |
 |
 |
 |
| 投稿日:2023年4月5日 |
| タイトル:八ヶ岳に咲く花・ぬり絵図鑑 |
 |
**マンサクって?**
★マンサクは、春一番に「まず咲く」と言う所から「マンサク」、と言う名前になりました。
★春浅い時期に林の中でふんわりとした黄色が目を引き、春の訪れを感じさせてくれる花です。
★同じく、この時期にやはり黄色の花を咲かせるものに「ダンコウバイ」があります。明るく元気がでるかわいらしい花です。また、どちらも秋の紅葉も綺麗です。
|

プリントアウト用PDFファイル(A4縦1ページ:451KB)

|
 |
 |
 |
 |
 |
| 投稿日:2023年4月5日 |
| タイトル:八ヶ岳に咲く花・ぬり絵図鑑 |
 |
**フデリンドウって?**
★花のつぼみの形が筆のように見えるので、この名前が付きました。
★フデリンドウは春に花を咲かせて種をまき、それが秋に芽をだします。その芽は落ち葉などの下で冬を過ごし、春になると伸びて花芽を付け、花を咲かせます。これを越年性1年草と呼びます。乾いた草地や林に育ち、10cm程の大きさになります。
★似た仲間にハルリンドウ・センブリ・アケボノソウなどがあります。
|

プリントアウト用PDFファイル(A4縦1ページ:364KB)

|
 |
 |